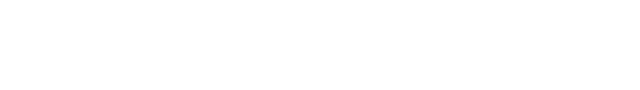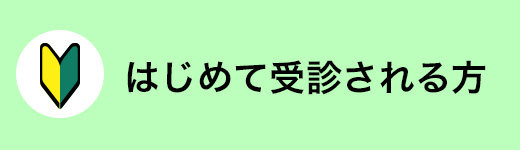腎臓病を守る<糖尿病性腎症> その2
糖尿病があり、それにより腎臓の機能が影響を受け、腎機能低下速度が増していく状態。
この状態を糖尿病性腎症と呼んでいます。
アルブミン尿の出現 → 持続性蛋白尿 → 腎機能低下 → 末期腎不全
という流れが典型的です。
実際には、高血圧や腎炎などでも腎機能は影響を受けていきます。
前回ブログ その1 を読まれていない方は先にそちらを御覧ください。
そこでは薬剤での治療として、
ARB
SGLT2阻害薬
フィネレレノン
の3つを挙げました。
これをどう使い分けるか、ということがときに議論されていましたが、
下2つのSGLT2阻害薬とフィネレレノンを2つ同時に使うのがよさそうだ、という報告がつい最近でました。
CONFIDENCE試験です。
SGLT2阻害薬としてエンパグリフロジン(商品名 ジャディアンス)と
フィネレレノン(商品名 ケレンディア)
の2つを用います。
誰に>>2型糖尿病を合併した慢性腎機能障害の患者さんに対して
何を>>エンパグリフロジン、フィネレレノンを
どうする>>それぞれ単剤と、2つ同時で服用した場合で
どうなる>>尿中アルブミンがどれくらい減るのか
安全性はどうか?
を比較した論文です。
尿中アルブミンが減る、ということはきっと腎臓を守ってくれるだろう、という推測の根拠になります。
ARBをできるだけ服用しているうえでの比較です。
つまり、いいと言われている薬3つをしっかり使うとどうか、ということです。
追跡期間は180日。半年で差が出るか、ということです
180日経ったら、投与を中止します。
その後 30日間、どういう経過をたどるか観察しています。
結果は。
ARB(腎臓保護薬として全例使用)に加えて
エンパグリフロジンだけ足したときとフィネレノンだけ足したときでは
ほぼ効果は同等。
3剤を全部併用するとしっかりアルブミン尿が減る。
中止すると、1ヶ月で飲んでなかったころと同じくらい、もしくは少し良いかな、という程度に戻るということが見て取れます。
この尿中アルブミンクレアチニン比 UACR といいますが
治療して30%以上低下したらその後の腎臓トラブルが1/3減る という強力な根拠論文があります。
Am J Kidney Dis. 75(1): 84-104. Published online August 28, 2019.
副作用に関して、懸念される点は2つ。
1.電解質 カリウム K が上がりすぎないか。
2.血圧が下がりすぎないか。
です。
それぞれ見ていきます。
まずはカリウム。
基準値はだいたい 3.5〜4.9くらい。
それがいくつ上がるか、が注目点です。
エンパグリフロジンではほとんどあがらない。
フィネレノンでは0.2くらい上がる。
2つ合わせて使うともっと上がる。
それでも0.25〜0.30 くらい。
しかも治療はじめにその変動は見られる。
つまり臨床上ではいくらでも調節できる程度です。
治療が始まったら、2週間目、4週間目は注意が必要で、その後はには大きな変動は来しにくそうです。
もともと腎臓機能低下への治療なので、カリウムが上がりやすい方が対象です。
十分に対処可能な範疇です。
血圧は?
はい。
両方足すと血圧が7mmHg程度下がる、という結果でした。
辞めるともとに戻ります。
糖尿病の方では、高血圧の治療も一緒に必要なことは多いです。
この変動のクセと下がり幅を知っていれば、やはり対処可能な範疇です。
血圧の薬を一つやめられることも期待できます。
前回ブログの話と合わせて考えると、糖尿病で治療を行っているときには
>定期的に蛋白尿 できればアルブミン尿 が出ているか見る。
>eGFRを定期的に見ておく。
>腎機能低下を食い止める必要が出たら、早めに対処する。
>早めとは、症状が出るまえ、自覚が出る前。
>治療を途中で止めると、もとに戻ってしまう可能性がある
ということを考えます。
こういった論文を見たときに考えることがいくつかあるのでそれも付け足しておきます。
アルブミン尿が減ったからと言って本当に腎臓が守られるのか?
もっともな疑問です。
たとえばこの論文はPhase 2といって、有効性がありそうかどうか。
安全性が大丈夫そうかどうか、を探ったものです。
おそらくこのあと、phase 3ということで、もっと長期に調べ、薬を飲まなかった方々と3剤を併用した方での
eGFRの比較、透析導入へ至るまでの期間の比較、などが調べられていくと思われます。
ですので、2025年6月では、きっと有効だろう、ということまでがいえる点になります。
なぜ180日で止めたのか?
これももっともな疑問です。
この論文自体が180日での有効性、というデザインだということです。
それはどういうことかというと
短期間の変化で治療効果を反映できる
というコンセプトがあるので。この尿中アルブミンの推移を比較した、ということです。
いままでの治療方針が変わる可能性があるのか?
腎臓を守ろう、と考えたとき、まずはARB.
そして、糖尿病の治療でもあるから、ということでエンパグリフロジンを始めて、しばらく様子を見ておく、というのが定石です。
それでも腎機能が落ちてきたら、じゃあ、まあ、フィネレノンを考えようか。
でも症状もないし、患者さんも薬増えるのも嫌そうだし、という迷いが生じることがありえます。
段階的に治療を強化する方法でいいのか?
という曖昧な思考を、最初から併用することでの有用性を検討している、という点で臨床医としては参考になります。
だって、腎臓の機能が落ちてきたら、ということでは、もとに戻せない現状では、迷っていた時間=腎臓がどんどん機能低下している期間 と言えるかもしれません。
安全性が確保され、管理できる状況であることも重要です。
有効性と安全性のバランスをみて、プロとしてこの状況ではこういう併用がメリットが有り、デメリットが少なく、症状がなかっとしても、先の自分を守ることが期待できる、といえる根拠のひとつかもしれません。
今回は、糖尿病のかたの腎機能を守る、というテーマで2回にわたり記載しました。
難しい話ですが、当院に来られる患者さんには有効性と安全性をしっかり配慮し、長い期間をかけてでもしっかり通っていただける、かかりつけ医、というものを目指しています。
普段、糖尿病や高血圧などで治療を受けられている方が、お腹が痛い、とか、風邪引いて熱出た、とかそういったことで当院を受診していただくとき、急なお困りごとで頼っていただけるのはとても光栄に感じています。
かかりつけ医の姿というのを考えています。