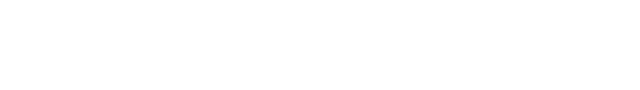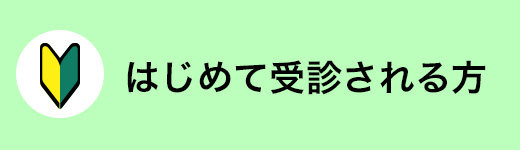糖尿病治療方針についてのメモ その2
本日のテーマ;内服薬と注射薬 どっちがいいの?
GLP1受容体作動薬、というのは聞き慣れない表現かもしれません。
薬剤名で言えば、リベルサス(セマグルチド 内服薬)とかマンジャロ(チルゼパチド 週一回の注射薬) というものがあります。
前回ブログで、こうお書きしました。
内服薬、注射薬、効果は似たようなもの、と思っていますが細かく見ると信頼性が異なると思っています。
リベルサスは、3mgから開始し、7mg,15mg と数週単位で増量していきます。
マンジャロは、週一回、2.5mg投与し、必要に応じて 5mg 10mgと増量していきます。
Buckley et al., Sci. Transl. Med. 10, eaar7047 (2018)
この論文の中で、リベルサスは胃から吸収されるよ! という解析されています。
じわじわと、薬が吸収されているイメージです。
ただし、食中食後、つまり胃の中に食べ物があると、まったく吸収されません。
下のグラフは、食後服用では、リベルサスの血中濃度が、全く上がらない、という解析結果です。
濃度の上昇がなく、真っ平ら、です。
服用しても効果がまったくない、ということです。
では。
薬の添付文書にも書いてあるように空腹時に服用すればしっかり吸収されるのか。
効果が出るのか、という点です。
その解析が以下のグラフです。
Fasting stateというのは空腹時、ということです。
濃度が高いところから低いところまで、様々です。
つまり、吸収・血中濃度上昇にかなりばらつきがある、ということです。
早朝空腹時にわざわざ服用したのに、吸収されたりされていなかったり、ということです。
なぜそんな事が起こるのか?
これはこの薬剤がもともとセマグルチド単体では、内服では全く吸収されないのを、SNAC という吸収促進剤と組み合わせることで、胃だけで吸収できるように作られていることが要因にあります。
人により、胃の活動具合が違ったり、胃の中のpHのバランスが変わっていたり、水を飲むとこのSNACの働きが落ちたり。
アイデアとそれを内服薬製剤までこぎつけたのはとてつもない努力があったものと思います。
でも、ちょっと不安定なので、もったいないです。
注射薬はどうか?
別の論文です。
https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2021.100387
この論文の中で、同じ薬剤ですが、内服薬と注射薬の血中濃度の比較が行われています。
下のグラフです。
左3つは、内服での濃度のばらつき。
右2つは、注射での濃度。
一目瞭然です。
左3つのばらつきからは、ほとんど効いてないだろうという濃度からかなりよく濃度が上がっている人まで様々です。
内服3mgでよく吸収される人は、14mgであまり吸収されない人の濃度差が20倍くらいあるように見えます。
一方、注射では濃度の予測ができる イコール 効果が予測できる くらいの安定性が見て取れます。
なので、しっかり効果を出したい、安定した結果がほしい、せっかく時間とお金をかけて治療に尽力するなら内服薬より注射薬が望ましい、というのは言いすぎでしょうか。
糖尿病で注射、というとネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃいます。
気持ちはわかります。
でもインスリンの注射とは、投与している薬剤は違います。
同じ薬剤なら、効果が安定して発揮される方が望ましいと考えています。
それが、糖尿病に伴う将来の腎臓病、心血管病のリスクを減らしてくれるのならなおさら。
GLP1受容体作動薬を用いるときには、内服は手軽です。
でも、朝起きてすぐ服用して、30分は水さえ飲めません。
注射は一週間に一度、一瞬チクンです。
上記の諸々のデータを踏まえて考えています。
というすべてを省いて
「できれば注射薬での治療をおすすめします」、とお話しました。
以上、先日患者さんからいただいたご質問の
内服薬と注射薬、どっちがいいの? へのお返事です。