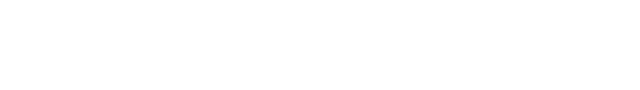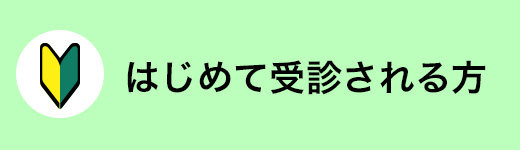冠微小循環障害
冠微小循環障害(CMD)の話です。
CMDとは
心臓に酸素と栄養を運ぶ「冠動脈」には、カテーテルやCTで見える太い血管(心外膜側)と、顕微鏡レベルの細い血管(微小血管)があります。
冠微小循環障害(CMD)は、この微小血管のはたらき(拡がり方・抵抗・攣縮)がうまくいかず、心筋が相対的に酸素不足になる状態です。
よくある自覚症状
-
階段や小走りで出る胸の圧迫感、息切れ
-
安静時や夜間に起こる胸部不快感(数分〜15分程度)
-
ストレスや寝不足、寒さで悪化する
-
検査で「血管はきれい」と言われたのに、症状が続く
当院での検査の流れ
順に確かめます。
ステップ1|まずは症状
胸が締め付けられる
息切れしたり改善したり
安静にしているのに、胸が苦しくなる
胸の症状とともに左腕が痛くなったり重くなったり。
胸の症状とともに、アゴや歯茎の具合がおかしくなる
胸が圧迫される感じ,詰まる感じ,締め付けられる感じなどが多く,激しい胸の痛みで冷汗を伴うこともあれば,漠然とした胸の違和感くらいに弱い症状のこ ともあります。
こういった症状は狭心症に典型的な症状であります。
症状をよくお聞きして、患者さん自身でも気にしてなかったような変化の確認をします。
痛みは前胸部を中心に生じますが,奥歯や顎,左肩から左腕に及ぶこともあり ます。
痛みは数分ほど持続することが多く,ニトログリセリンの舌下(舌の下に入れて溶かし ます)で速やかに消失します。
胸痛を自覚した後に一時的に意識を失うこともあります(失神)。
冠攣縮が長く持続すると心筋梗塞を発症することもあり,またきわめてまれに突然死に至るこ とがあります。
ステップ2|太い血管の狭窄を除外
心電図・心エコーを行います。
ホルター心電図も必要なことがあります。
あるいはすでに検査を受けたものの、異常がなかった、と確認されていることもあります。
重要なことは、【症状がある真っ最中に検査を受けれたか】です。
発作の真っ最中には異常があるものの、症状が収まっているときには、これらの検査では異常がないのことが通常です。
心電図や心エコーでは、心臓のダメージがないかどうか、基本的な心臓の機能を評価します。
ホルター心電図では、検査時に発作があれば、症状の原因がよくわかることが多いです。
そのうえで、冠動脈CT(CCTA)で50%以上のはっきりした狭窄がないかを確認します。
ステップ3|虚血の客観的な証拠
虚血とは、つまり心臓の筋肉にいきわたる血液が不十分、ということです。
-
負荷試験(点滴で薬剤投与しながらのエコー検査 運動検査)
-
核医学(SPECT)や心筋MRI(負荷パーフュージョン)
これらで「心筋に血流不足が起きているか」を可視化します。
ステップ4|“どのタイプのCMDか”を特定(連携施設で実施)
-
冠動脈の細いワイヤーで冠血流予備能(CFR)や微小血管抵抗(IMR)を測定
-
アセチルコリン(ACh)誘発試験で、微小血管が攣縮しやすい体質かを確認
当院で非侵襲的評価を進め、必要に応じて提携病院での侵襲的冠機能検査をご案内します。
※「狭窄はないのに虚血がある」方ほど、この系統的な評価で原因が明確になります。
ただし、ハードルがいくつかあります。
入院が必要。
血管の中にカテーテルをいれる必要。
多少のリスクがある薬剤を投与が必須。
検査中に脈が非常に遅くなることがあるため、ペースメーカーを一時的に入れることがおおい。
という点があります。
そのため、典型的な症状、虚血の証拠、冠動脈CTで血管が詰まっていない、という条件が揃っている場合には、カテーテル検査は見合わせ、治療に進むこともあります。
治療:タイプに合わせて“効く治療”を選ぶ
1)生活・心臓リハビリ(全員におすすめ)
-
禁煙、節酒、十分な睡眠・ストレス管理
現代社会はストレス社会です。
ですので、ストレスゼロは困難です。
ストレスを発散する、という意味になります。 -
有酸素運動:息が上がりすぎない中〜やや強めの強度で、1回20〜30分、週3回以上(できれば毎日)
「運動する時間がない」という生活そのものがリスクになっている可能性もあります。
散歩は有意義です。
通勤時間を、この有酸素運動としてはカウントしにくいです。
想定しているのは、歩いたあとに、自然と気持ち良い運動だった、と感じるようなタイプの運動です。
出勤して、会社について、気持ちいい出勤だった、と感じる方は少ないように考えます。
運動すると心臓が心配な方、運動で症状が出る方は強度を一段階下げ、クールダウンを長めにすると楽になります。 -
血圧・脂質・血糖の最適化
生活習慣生活習慣、とよく聞きますが、日々の生活の結果が血管病、という考え方もあります。
2)薬物治療(タイプ別に最適化)
-
微小血管攣縮(スパズム)優位:カルシウム拮抗薬を軸に、症状パターンに応じてニコランジル、硝酸薬などを調整します。
血管拡張薬は、飲み始めに頭痛を感じます。
いわゆる頭痛薬が効きにくいタイプの頭痛ですが、徐々に慣れていきます。
医師とよく相談の上、服用継続を相談されるのが良いです。
-
拡張不全・抵抗上昇(拡がりにくいタイプ):β遮断薬を基本に、ACE阻害薬/ARB、スタチンなどで内皮機能・微小循環の質を整えます。
心エコー検査や冠動脈CTで、動脈硬化状態、冠動脈石灰化状態などの結果と合わせて、治療内容は調整されます。
基本的に、血圧を下げる効果のある薬剤なので、少量から初めて調整になります。
そのため、少量から投与、というやり方では、必ずしも治療を始めてすぐに症状が消失するわけではありません。
副作用などがないかどうかを見極めつつ、投与量が調整されます。
内服薬の量が増えると、病状が悪くなった、と感じる方もいますが、はじめが非常に少ない量から始めていることも多く、よく説明を聞かれるのが良いです。
-
併存症(高血圧、糖尿病、脂質異常、睡眠時無呼吸、肥満、貧血、甲状腺機能など)を並行して是正することが、症状改善に直結します。
- 症状があるときにはニトロ投与が有効です。
胸痛は動いているときにも、安静時にも起こることがあります。
さらに、10分以上持続することもあります。
ニトログリセリンの舌下投与の効果が乏しい例も多く存在します。
3)フォローアップ
-
症状日誌(発作の頻度・誘因・持続時間)を共有し、運動量と薬の微調整をこまめに行います。
当院では、血圧手帳や心不全手帳を用いて、症状の状況を患者さんとともに把握していき、治療内容を調整します。 -
必要に応じて再評価(エコー・負荷検査・画像)を行い、長期的なリスク管理につなげます。
よくある質問(Q&A)
Q. CTで「異常なし」でした。心臓は原因ではない?
A. 「太い血管の詰まりがない=原因がない」ではありません。
微小血管レベルの機能異常はCTでは見えにくく、負荷検査やPET/MRI、冠機能検査で初めて分かることがあります。
Q. ストレスや寒さで痛むのはなぜ?
A. 攣縮の素因があると、交感神経緊張・寒冷刺激・過換気などで小さな血管が一時的に縮みやすくなります。
深い腹式呼吸、入浴・保温、運動強度の調整が予防に役立ちます。
Q. どのくらいの人が当てはまりますか?
A. 「狭窄はないのに胸痛が続く」方の中では、冠攣縮やCMDが単独/混在していることが少なくありません。
系統的に調べると初めて内訳が分かるケースが多い印象です。
受診の目安
-
太い血管は問題なしと言われたが、胸の圧迫感・息切れが続く
-
ストレスや寒さ、寝不足でぶり返す
-
運動を始めるとすぐ苦しくなる、治療中なのに「詰まった感じ」が残る
- どこ行っても、ストレス、精神的なもの、気のせい、検査は正常、と言われるものの、症状が一向に良くならない。
一つでも当てはまる場合、“見えにくい原因=微小循環のトラブル”が隠れているかもしれません。
戸頃循環器内科クリニックでは、上記のステップでしっかり診察・診療を行っています。
心電図・心エコー・必要に応じた冠動脈CTなどがすぐに検査可能です。
結果に合わせて、運動療法と薬物療法を適宜、最適化していきます。
-
CMDは“細い血管”の不具合による心筋の血流不足。
-
狭窄の除外 → 虚血の可視化 → 冠機能(タイプ)同定が診断の筋道。
-
生活習慣改善+タイプ別の薬物最適化で、症状と生活の質の向上を目指します。
ご相談や検査のご希望は、受付・お電話・Web予約からお気軽にどうぞ。