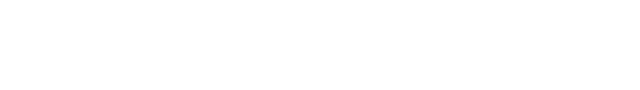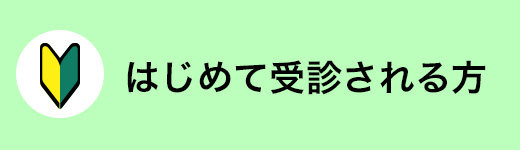心不全の診断・ステージ分類
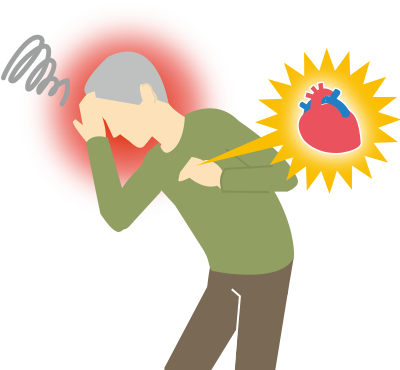 心不全とは,心臓が悪いために,息切れやむ くみが起こり,だんだん悪くなり,生命を縮 める病気です。
心不全とは,心臓が悪いために,息切れやむ くみが起こり,だんだん悪くなり,生命を縮 める病気です。
もっと細かく言えば、心臓の形態的機能的な異常が起こるせいで、心臓のポンプ機能が保てなくなり破綻した状態である、とも言えます。
呼吸が苦しい、だるい、主に足がむくむ、などが起こりそれによって運動能力が低下する状態です。
日本では、2017年に心不全ガイドラインが改訂となり下記の考え方が提示されました。
これは海外ではさらに数年前から言われていた考え方で、日本でもやっと取り入れられ、いまでは広く浸透した考え方です。
急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)
(日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン)より
心不全の病期によりA,B,C,Dとして、4つのステージに分けて考えるのが特徴です。
それぞれの特徴があり、お身体の状態やそれに伴う治療の目標が異なるのが重要な点です。
ステージA: 心不全になるリスクがあるものの、心臓の機能・構造自体には異常がない状態です。
リスク、とは高血圧、糖尿病、脂質代謝異常、喫煙などがあります。よくできる部分はしっかり管理治療を行うことで、それより悪化しないようにするのが目標です。
ステージB: すでに心臓自体にトラブルが発生してきている時期です。
狭心症を発症されていたり、心肥大、左室肥大、左室収縮能の低下、弁膜症(血液の逆流や弁狭窄など)が見られる状態です。
心エコー検査を行なえば、左室肥大や左室収縮能の評価は容易です。
重要なことは、ステージAとBは、心エコー検査や心電図、レントゲンなどで評価を行わないと区別がつかない、ということです。
高血圧で薬を飲んでいるが、心エコー検査を受けたことがないとすれば、ステージAかBなのか判別が難しいですから、目的や状態に応じたきめ細かい治療ができているかどうかは、難しいところとなります。
この時期はPre heart failure stageと呼ばれています。
つまり前心不全期、ということです。
この時期の治療目標は、心不全発症を予防する、心不全で入院するような目に合わないようにする、ということです。
ステージC: 心不全ステージです。
呼吸困難等を発症してしまい、苦しい、だるい、むくむ、などの症状が現れます。
薬物治療のみならず食事運動療法をかなり厳密に調整しますが、1−2割の方はまた入院する事があります。
2020年代でも、心不全入院後、治療して退院となっても、その後の再入院してしまう方はゼロにはなっていません。
心臓の機能が低下すると、なかなか回復しにくい、という面もあります。
ステージA、B の間にしっかり予防治療を行うことの重要性が強調される根拠ともなっています。
治療の目標として、症状が治まること、QOLが改善すること、再入院を回避するとこ、寿命を取り戻すこと、などがあげられます。
一気にたくさんの目標が発生します。治療も管理も医療従事者側のサポート体制も重要になります。
ステージD: 治療抵抗性心不全ステージ、あるいは難治化ステージと呼ばれます。
様々な治療を行っても症状が改善しない、良くならない、という時期です。
補助人工心臓や心臓移植などの特別な治療を検討します。
もしくは、終末期ケア、緩和ケアといった苦しさを取り安らぎを取り戻すことがこの時期の目標となります。
強いサポートと信頼関係が必要です。
患者さんのその人らしさ、誇り、安らぎなどの面をしっかり支えるという考え方が重要になります。
病院に通院して治すことを求めた医療より、在宅医療や訪問看護、訪問リハビリなどのケアを考える時期です。
もう一つの心不全の分類では、左室収縮能に応じた分類があります。
よく広がりよく縮む左心室は、たくさんの血液を送り出すポンプ機能が優れていると言えます。
逆にあまり広がらず、あまり縮めないと血液を送り出す機能が低下していると言えます。
左室の収縮する能力をLVEF(Left ventricular ejection fraction)といい、%表示をします。
心不全別に3つに分かれています。
LVEF 50%以上の HFpEF へふぺふ
LVEF 40-49% HFmrEF へふえむれふ
LVEF 39%以下 HFrEF へふれふ
と呼ぶのが一般的です。
診断
症状と既往歴(リスクが有るかどうか)、家族歴、身体所見として聴診、足のむくみ、心雑音などを確認します。
さらに、検査として、血液検査(特にBNP NTProBNPという項目で心臓への負担を確認)、心電図、胸部レントゲンや心臓エコー検査等で心臓機能の評価、心不全の原因特定および治療を行い、治療の効果判定を適宜行い治療の調整を行います。
心不全の原因は様々なので、心臓CTを行うこともよくあります。
これらのプロセスにより、心不全の確定診断、もしくは心不全ではない、という診断を行い、原因疾患別や心不全ステージに応じて治療を行います。
あるいは心不全ではないが症状がある場合には、その原因を追求し治療に進みます。
必要に応じて心不全の発症予防や経過観察となることもあります。